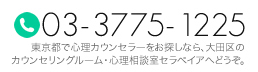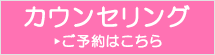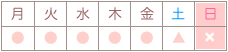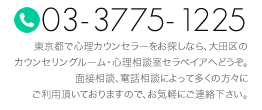アダルトチルドレンにカウンセリングは効果的?特徴や原因も詳しく解説!
「アダルトチルドレンにカウンセリングは効果的?」
「そもそもアダルトチルドレンってどんな状態?」
「アダルトチルドレンになってしまう原因を知りたい!」
アダルトチルドレンという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
親とのある関わりによって、ほかの対人関係においても問題が生じてしまい、生きづらさを感じている人の俗称です。
本記事では、アダルトチルドレンの特徴や原因、 効果的な治療方法について、詳しくお伝えしていきます。
カウンセリングを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「アダルトチルドレン」とはどんな状態を指す?
まずは、アダルトチルドレンがどのような状態を指すのか解説しておきましょう。
「アダルトチルドレン」とは、もともとは「アルコール依存症者を抱えた家族のなかで育った大人」という意味でした。
その後、アルコール依存の問題のみならず、機能不全家族のなかで心的外傷を受け、それが癒されることがないまま成長し、生き苦しさに悩む大人を指すようになりました。
悪い家庭環境のせいで、精神的には子どものまま大人になってしまった人というような意味合いです。
最近の世相に照らしていうならば、いわゆる宗教2世とか、カルト2世とか呼ばれる人達もこの範疇に入るかと思います。
医学用語ではありませんので、明確な定義はありません。
しかしながら、そもそも心の病は個人差が大きく、アバウトな部分が多いものです。
アダルトチルドレンという俗語が、専門用語以上に現代人の心の病理を言い当てているということで、1990年代にアダルトチルドレン関係の出版ブームがありました。
アダルトチルドレンの本を読んで、自分も当てはまると思ったらアダルトチルドレンなのです。
アダルトチルドレンの5タイプ
アダルトチルドレンはアバウトな概念であり、抱えている問題は人それぞれですが、大よそのカテゴリー分けはできるものです。
アダルトチルドレンの代表的なタイプは以下のとおりです。
- 完璧主義者型:生活において完璧であろうとするタイプ
- 自責・被害者型:家族のなかで悪者になろうとするタイプ
- 虚無型:自分の存在を消そうとするタイプ
- 世話型:家族の世話を自分一人で引き受けようとするタイプ
- 道化型:家族を笑顔にするためにピエロを演じるタイプ
アダルトチルドレンの4つの特徴
アダルトチルドレンがどんな状態かわかったところで、アダルトチルドレンの概要をさらに深掘りしていきましょう。
アダルトチルドレンの特徴としてよく挙げられるのは、以下の4つです。
- 精神障害
- 人間関係が極端
- 生きにくさを感じる
- 世代間連鎖
それぞれ確認していきましょう。
特徴①精神障害
アダルトチルドレンの特徴1つ目は、精神障害を抱えやすいというものです。
アダルトチルドレンがなりやすい精神障害としては、以下のような例が挙げられます。
- 不安障害
- 気分障害
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- うつ病
- 適応障害
- 双極性障害
- 境界性パーソナリティ障害
- 自己愛性パーソナリティ障害
- 解離性障害
こちらの記事ではうつ病について詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
参考記事:うつ病にカウンセリングは効果的?うつ病についても詳しく解説!
特徴②人間関係が極端
アダルトチルドレンの特徴2つ目は、人間関係が極端になってしまうというものです。
過度に親密な付き合いを避けたり、過度に人に依存したりします。
また、通常の人間関係を築いていたりしても、心から信用すること信頼することができず、表面的な付き合いになってしまいがちです。
こちらの記事では依存症の特徴や原因、 効果的な治療方法について詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
参考記事:依存症にカウンセリングは効果的?特徴や原因も詳しく解説!
特徴③生きにくさを感じる
アダルトチルドレンの特徴3つ目は、生きにくさを感じやすいというものです。
アダルトチルドレンは自己評価や自尊心は非常に低いことが多いです。
そのため、自分自身のことを大切にできなかったり、物事を楽しめなかったりし、結果生きづらさにつながります。
特徴④世代間連鎖
アダルトチルドレンの特徴4つ目は、世代間で連鎖する、つまり、親が抱えていた心の問題を子供も引き継いでしまうということです。
「依存や虐待の世代関連鎖」が多くの家庭で起きていることが、臨床心理の現場で明らかにされてきました。
アルコール依存症の親や虐待をする親のもとで育った子どもは、大人になってから親と同じ問題行動を繰り返すことが多いとされているのです。
アダルトチルドレンになってしまう5つの原因
ここまで、アダルトチルドレンの特徴を4つ見てきました。
ここからは、アダルトチルドレンになってしまう原因を以下の5つに絞って解説していきます。
- 過去に虐待を受けていた
- 毒親
- 機能不全家族
- 親がアルコール依存症
- 体質
それぞれ解説していきます。
原因①過去に虐待を受けていた
考えられる原因の1つ目は、過去に虐待を受けていたというものです。
一口に虐待といっても、その種類はさまざまです。
身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、育児放棄であるネグレクトなど。
また、ネグレクトにも一般的に知られている食事を与えないもの以外に、必要な医療を受けさせない医療ネグレクト、必要な教育を受けさせない教育ネグレクト、子どもの金銭を搾取する経済ネグレクトなどの種類が存在します。
原因②毒親
考えられる原因の2つ目は、毒親による教育です。
近年では「親ガチャ」という言葉も聞くようになりました。
毒親とは、子どもに悪影響を及ぼす親、一般的に良いとはいえない教育方針によって子どもの心理的負担になる親を指します。
たとえば、束縛ともとれる過保護な親もある種の毒親でしょうし、子どもの将来を狭めるような英才教育や進路決定も毒親の行動とされます。
原因③機能不全家族
考えられる原因の3つ目は、機能不全家族であることです。
機能不全家族とは、日常的にストレスが漂っている家族のことを指します。
虐待のある家庭はもちろん、頻繁に喧嘩が起こっていたり、常に誰かが誰かの顔色を伺っていたり、情緒不安定な親がいたりする家庭が該当します。
原因④親がアルコール依存症
考えられる原因の4つ目は、親のアルコール依存です。
親との関係や親からの対応によってアダルトチルドレンは生まれます。
毎日泥酔して子供を放置したり、アルコールを入手するために生活費まで削ってしまったりする親の子どもはアダルトチルドレンになりやすいといえます。
原因⑤体質
考えられる原因の5つ目は、本人の生まれ持った体質や気質です。
子どもは全般的に衝動的な生き物ですが、その度合いは人それぞれ違います。
そして、より衝動的だったり敏感だったり気難しかったりといった子どもの性質が、親のストレスとなり、結果子どもへの対応も悪くなってしまうのです。
カウンセリングをはじめとするアダルトチルドレンの治し方
ここまで、アダルトチルドレンになってしまう原因を5つの観点から見てきました。
最後に、アダルトチルドレンの治し方について解説していきます。
主な方法として挙げられるのはカウンセリングですが、ここではそれ以外の2つを含めた以下の3つの方法を解説します。
- 薬物療法
- 自助グループ
- カウンセリング
それぞれ解説していきます。
治し方①薬物療法
先ほど解説したように、アダルトチルドレンはさまざまな精神疾患を患う可能性が高いです。
不安感、抑うつ気分を軽減させる薬の処方はアダルトチルドレンの治療の一歩として期待できます。
治し方②自助グループ
同じアダルトチルドレンがお互いに支え合う自助グループへの参加も一手です。
共感しあえるだけでなく、人間関係構築の練習にもなります。
アダルトチルドレンは、ACという言葉で広まり、ネット上でも交流の場があります。
治し方③カウンセリング
アダルトチルドレンは人間関係の病気です。
自分がなぜ生きづらさを感じているのか、なぜ人間関係で問題が起きるのか、心の奥底にあるモヤモヤしたものは何なのか…自らの内面を見つめる作業が必要です。
自助グループもとても有効なツールですが、グループは苦手という人も多いのです。
専門のカウンセラーに話を聞いてもらい、コメントをもらうことで、新しい気づきが生まれ、自己内省が深まっていきます。
さらにトラウマ治療やイメージワークなどを用いて心の中のトラウマを癒していきます。
アダルトチルドレンはカウンセリングで治る
アダルトチルドレンは診断名として確立されていないことから、ほかの精神障害や精神疾患と違い本人も気づきにくいケースが多いものです。
しかし、カウンセリングは本来病気や障害がある人のためだけのものではありません。
なんとなく生きづらい、自分らしい生き方が分からない、毎日がつまらない、人と会うのがおっくうだ…そのような感じがしたら是非カウンセリング機関に相談してください。
心理相談室セラペイアでは、アダルトチルドレン問題の根底にあるトラウマを解消し、本来のあなたらしい生き方ができるようにサポートさせて頂きます。
カウンセリングをご希望の方は、お気軽にご相談ください。