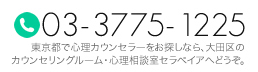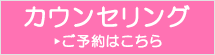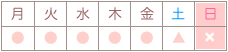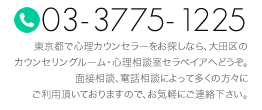パニック障害とは? 治療はカウンセリング?
「パニック障害とは?」
「パニック障害の治療法としてカウンセリングは有効?」
「パニック障害の予防方法や対処法を知りたい!」
パニック障害という言葉から、あなたはどんな様子をイメージしますか。
実際にパニック障害の全容を知っている方は少ないかもしれません。
そこで本記事では、パニック障害の特徴から、パニック障害が起きる理由、その予防方法や対処法まで詳しくお伝えしていきます。パニック障害の方や、周りにパニック障害の方がいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
パニック障害とは
はじめに、パニック障害とは何かについて、その特徴から詳しく解説していきます。
以下3つの主症状を軸に見ていきましょう。
- パニック発作
- 予期不安
- 広場恐怖
それぞれ詳しく解説します。
症状① パニック発作
パニック発作とは、突然訪れる恐怖心や強い不安感によって、激しい動悸や呼吸困難などが起こる症状のことです。また、場所や状況にかかわらず起こるため、睡眠中に発作が起こる場合もあります。
実は、パニック発作は心筋梗塞の症状に似ています。そのため、「自分はこのまま死んでしまうのではないか」と強い恐怖心を抱き、救急車を呼ぶ患者さんも多くいます。
しかし、心臓などに異常があるわけではありません。
症状② 予期不安
予期不安とは、パニック発作を繰り返すことで「また発作が起きるのではないか」と感じる症状のことです。
パニック発作は、時間が経つとまた繰り返す場合があります。
パニック発作がたびたび起こることで、次の発作を恐れるようになります。
「次は発作が治まらないのではないか」「今度こそ死んでしまうのではないか」と考えはじめ、先駆けて不安感が襲ってくるのです。
また、その不安のあまり、仕事を辞める、引きこもるなどの行動に至るのも予期不安の症状です。
症状③ 広場恐怖
突然起こるパニック発作を恐れ、外出を避けたりすることを「広場恐怖」といいます。
発作は自分の力で落ち着かせることができないため、他人からの助けを得たくなります。
そのため、理解者のいない場所やヘルプを得られない環境を極端に恐れ、広場恐怖を感じるのです。
広場恐怖になると「発作で恥をかくのではないか」「誰も助けてくれず死ぬのではないか」という心理状況になります。ショッピングモール、1人での外出、電車など、人によって広場恐怖を感じる場面はさまざまです。
また、広場恐怖が強くなると日常生活が困難になります。
外出ができなくなるため、仕事ができなくなったり、ひきこもりになったりと人間関係にも影響が出てきます。
そして、そんな自分を情けなく思う気持ちも強まってしまうのです。
パニック障害が起きる理由
パニック発作とは、死を避けるために起こるものです。
火事や突然の事故など、生命の危機に直面したとき、パニック発作と同じ反応を起こすことが多くあります。
物事が冷静に考えられなくなり、突然大声で叫びたくなったり、嘔吐してしまったりします。
これらの反応は、災害から逃げるために起こるものです。
パニック障害では、そのような反応が日常的に起こります。
最近の研究では、パニック障害の原因は脳内ホルモンのバランスの乱れであることがわかってきています。
そのため、死の危険がないときでもパニック発作が起こるのです。
パニック障害(発作)の予防法や対処法
次に、パニック障害による発作に有効な予防法や、もし発作が起きてしまったときの対処法を見ていきましょう。
ここでは以下の4つを紹介します。
- 乗り物や部屋では出口の付近にいる
- 意識を向ける先を変える
- 深呼吸をする
- 生活習慣に気をつける
それぞれ解説していきます。
その① 乗り物や部屋では出口の付近にいる
電車やバスを利用する場合、扉の近くにいることをおすすめします。
とくに、通学や通勤で電車・バスを利用する場合は、日常的に意識するとよいでしょう。
扉の近くにいることで「何かあってもすぐ逃げられる」「もし発作が起こってもすぐ外に出られる」と確認できるため、不安が軽減されるのです。
その② 意識を向ける先を変える
パニック発作が起こると、心臓の鼓動や呼吸に集中してしまいがちになります。
このまま死んでしまうのではないかと強い不安に襲われるためです。
しかし、このような行動は、発作をよりいっそう悪化させてしまいます。
心臓の鼓動を確認すると余計に鼓動が高まってしまったり、呼吸を確認すると過呼吸が悪化してしまったりするためです。
そのため、パニック発作が起こった場合は意識を向ける先を変えることが重要になります。
意識の向け方は「頭の中で好きな曲を歌う」「時計の秒針に合わせて呼吸をする」などさまざまです。
自分に合った意識の向け方を見つけるとよいでしょう。
その③ 深呼吸をする
パニック発作で過呼吸になった場合、呼吸が整うと発作が治まることもあります。
そのため、深呼吸をすることも対処法として効果的です。
4秒吸って6秒吐く、鼻で吸って口で吐くなど、呼吸法はさまざまあります。
いずれにせよ、吐く息を長くして、規則的なゆっくりとした呼吸が効果的です。
その④ 生活習慣に気をつける
パニック障害患者は、生活リズムが崩れがちです。
パニック発作への不安から睡眠が不規則になるためです。
しかし、生活リズムが崩れると自律神経が乱れ、パニック発作が起こりやすくなってしまうのです。
そのため、決まった時間に就寝、起床し、規則正しく生活することを心がけると良いでしょう。
パニック障害の治療法はカウンセリング? お薬?
最後に、パニック障害の治療法について解説しておきます。
パニック障害の治療は、主に「カウンセリング」と「薬物療法」の2種類です。
それぞれの特徴、パニック障害に有効な具体的方法を紹介します。
こちらの記事ではカウンセリングを受ける際の流れや効果について詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
参考記事:カウンセリングとは? 受ける際の流れやメリットについて解説
パニック障害に対する薬物治療について
パニック障害には、薬物療法が効果的です。
薬物治療での1番の目標は、脳内物質のバランスを調整することでパニックの症状を起こさないようにすること。
次いで、予期不安などをできるだけ軽減させることも目標になります。
一般的に、SSRIをはじめとする抗うつ薬、 安定剤や抗不安薬がよく使われます。
SSRIは副作用が少なく依存性もありませんが、急に服用を中止すると断薬症状が出てしまいます。その断薬症状はパニック発作とよく似ているため、服用には注意が必要になります。
パニック障害に対するカウンセリング(心理療法)について
パニック障害の治療には、カウンセリングも重要です。
薬物療法と併用して一般的に用いられるカウンセリング手法は、認知行動療法というものです。
例えば、電車に乗る際にパニックを起こしてしまう人の場合、まず次の駅まで乗ってみて、大丈夫であれば、二駅三駅と距離を伸ばしていき、少しずつ自信をつけていくやり方です。
もっとも、パニック障害の人は、生育歴の中で問題を抱えており、心の中で存在不安、生きづらさを感じていることが多いものです。
そのような場合は、パニック障害の症状が出なくなっても、鬱や対人関係などの別の問題が出てきてしまいます。
カウンセリングによって、トラウマを癒すことはとても有効なことです。
さらに、自らの生き方を見直し、未来に向けての目標設定をすることでパニック障害は根本的に解消していきます。
心理相談室セラペイアでは、認知行動療法とともに、トラウマ治療に特化したFAPという手法を用いて、パニック障害の方に向けてカウンセリングをしています。
カウンセリングをご希望の方は、お気軽にご相談ください。