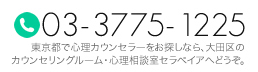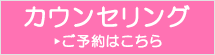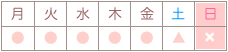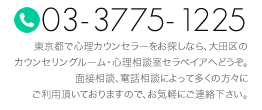カウンセリングを通してアンガーマネジメントはできるようになるのか
「アンガーマネジメントって何?」
「アンガーマネジメントはカウンセリングで可能?」
「アンガーマネジメントの方法を具体的に知りたい!」
人間誰しもが感じたことあるであろう「怒り」
しかし、怒りを良いものだと思う人は少ないでしょう。
そこで本記事では、怒りをコントロールする方法、アンガーマネジメントをカウンセリングの観点からお伝えします。感情コントロールのためにカウン リングを受けるか迷われている方は、ぜひ最後までご覧ください。
アンガーマネジメントとは
アンガーマネジメントとは、その名のとおり自らの「怒り(アンガー)」を「管理(マネジメント)」することです。
喜びや楽しさなどのいわゆる「よい」感情と違い、怒りはコントロールが効かなければ、人間関係など社会生活のあらゆる場面において悪影響となります。
怒りを出すべき場面、出すべきでない場面で、うまくその発現をスイッチできるようになりましょう。
怒りの感情のメカニズムとは
そもそも、怒りの感情とはどのような仕組みになっているのでしょうか。
以下の3項目によって解き明かしていきます。
- 怒りが発生する原因について
- 怒りを生み出す「一次感情」とは
- 「怒り」という感情が持つ性質とは
それぞれ簡単に見ていきましょう。
怒りが発生する原因について
怒りの原因は、突き詰めれば自分の中に存在します。
イメージしていた理想、期待、願望。
それらが壊されることで怒りが生まれるのです。
怒りを生み出す「一次感情」とは
怒りは、理想を壊された喪失への防衛手段です。
そして、私たちは守りとして怒りを発現させる前、何かしらの感情(=一次感情)を抱きます。
悲しい、悔しい、辛い、寂しい。
これらの感情を経て、怒りへとシフトしていきます。
「怒り」という感情が持つ性質とは
最後に、怒りの持つ性質を以下の4つに絞って紹介しましょう。
- 下の者に向くほど強くなりやすい
- 身近な人に向くほど強くなりやすい
- 周りの人に伝染する
- モチベーションにもなる
それぞれ説明していきます。
下の者に向くほど強くなりやすい
部下と上司に同じ行為をされて怒りを感じたとしましょう。
その怒りは、また怒りのぶつけやすさは、上司相手の方が小さいのではないでしょうか。
怒りは、立場が上の者から下の者へと流れやすいのです。
ちなみに「八つ当たり」もこの性質によって起こります。
身近な人に向くほど強くなりやすい
殺人事件でもっとも多い動機は「憤まん・激情」です。つまり、怒り。
そして、その8割以上が友人や恋人などの面識者、うち2割は親族です。
知っている人、親しい人ほど怒りは向きやすいということですね。
周りの人に伝染する
ポジティブな人がいるとその場は明るくなり、ネガティブな人といるとネガティブになります。
つまり、感情は容易に他人に伝染するのです。
とくに怒りはそれが顕著です。
他人がイライラしているのに対してイライラした経験がある方もいるのではないでしょうか。
モチベーションにもなる
怒りは、ときに人を殺してしまえるほどに大きなエネルギーを持っています。
しかし、その大きなエネルギーはマイナスだけでなく、プラス方向にも働き、奮起、努力、成長の糧になることもあります。
ですから、怒りのエネルギーそのものが悪いということではなくて、その暴発が怖いということなのです。
怒りを管理し、プラスの方向に向けることでより良い人生を創ることもできるのです。
アンガーマネジメントの手順
では、ここから実際にアンガーマネジメントを行う手順を解説していきます。
流れとしては、以下の3ステップです。
- まずは怒りの感情を自覚する
- 深呼吸により怒りの感情をコントロールする
- 徐々に考え方を変える
それぞれ簡単に見ていきましょう。
ステップ① まずは怒りの感情を自覚する
怒りをコントロールするためには、その瞬間に怒りの状態にあることを自覚しなければなりません。
怒っているとき、人は冷静さを欠いています。
難しいことは考えず、まずは「怒っている」という事実を把握することに注力しましょう。
ステップ➁ 深呼吸により怒りの感情をコントロールする
「把握」を経て、ようやく感情のコントロールに入ります。
怒りのピークは最初の6秒間に訪れるとされています。
様々なアンガーマネジメントの本にも紹介されていることですが、深呼吸が有効です。
吐く息を深く長くすることで、副交感神経が働きます。
深呼吸をすることで、怒りによる「衝動」をコントロールしましょう。
ステップ③ 徐々に考え方を変える
数回、深呼吸を続け、怒りが沈静化するのを感じつつ、自己内省してみて下さい。
自分の理想は何だったのか、それが壊されたときの一次感情(悲しい、悔しい、辛い、寂しい…)は何なのか、相手はなぜ自分の理想に反することをしたのか。
そこから、相手と自分の妥協点を模索するというように合理的な考えができるようになれるといいでしょう。
アンガーマネジメントの難しさ
もっとも、一般的なアンガーマネジメントの方法では、なかなか怒りをコントロールできないと思っている人達も多いでしょう。
前項で怒りを生み出している一次的な感情(悲しい、悔しい、辛い、寂しい…)について触れましたが、さらに突き詰めて考えると、人間は何らかのかたちで自らの社会的な立場、さらには生存そのものが脅かされるときに怒りを感じます。
古来より人間は、敵や猛獣に襲われたときに、恐怖心とともに身を護るために怒りが沸いてきます。
怒りの感情は、本能的なものであり、「必要だから」備わっているのです。
ですから、喜怒哀楽に代表される様々な感情の中で、怒りは特に根深くコントロールが難しい感情であるといわれるのです。
根深い怒りの根底にあるもの
一般的なアンガーマネジメントのやり方ではコントロールできない根深い怒りの根底には、当人も十分には自覚できていない何らかの恐怖心が潜在しているものです。
「見捨てられる恐怖」「批判される恐怖」「殺される恐怖」など…
そしてそれらは、生育歴の中で生じたトラウマによって生まれたものなのです。
心の中にトラウマを抱えていると、怒りのエネルギーが無意識に蓄積されていくことでコントロールできる容量を超えてしまい、往々にして破壊的な結果を招いてしまうことになります。
心理相談室セラペイアでは、トラウマ治療に特化したFAPという心理療法を用いて、根深い怒りであってもコントロールできるように導いてまいります。
さらに、適切な目標設定をすることにより、怒りの破壊的なエネルギーを未来に向けての創造的なエネルギーに変換することもできるのです。
心理相談室セラペイアでは、アンガーマネジメント以外のカウンセリングも受け付けています。
専門家によるカウンセリングをご希望の方は、お気軽にご相談ください。
大田区でカウンセリングをお探しの方は、蒲田駅・大森駅最寄りの心理相談室セラペイアまで、ぜひ足を運んでみてください!
こちらの記事ではトラウマとはそもそもどのようなものなのか詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
参考記事:トラウマによる心の傷はカウンセリングで克服できる?